このような悩みを持っていないだろうか。
・活性酸素は筋肥大の敵か味方かわからない。
・筋肥大はストレスなのでトレーニング後の抗酸化物質摂取は筋肥大を阻害するのでは?
この記事はこれらの悩みを解決していく。
この記事の内容は以下のとおりである。
1.活性酸素が筋肥大に貢献する理由を解説。
2.トレーニング後の活性酸素摂取の是非を考察。
この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者が解説しよう。
活性酸素が筋肥大に貢献する理由
活性酸素とは
活性酸素は不対電子を持つ非常に反応性が高い酸素中心の化合物の総称である。活性酸素は分子の安定化を図るために、タンパク質や脂質などと酸化還元反応する。これにより組織の酸化が引き起こされる。
活性酸素は単に細胞を傷つける有害物質ではなく、免疫細胞による病原体の除去や細胞内のシグナル伝達、遺伝子の発現調節や細胞の分化や発達といった役割を担う。しかし過剰に活性酸素が産出されると身体は酸化ストレスに陥り慢性的な疲労状態に陥る。
活性酸素は細胞を酸化させることで安定化を図るが、酸化した細胞は炎症を引き起こす。このように活性酸素が過剰に増加すると酸化ストレスと炎症が増加し身体は慢性的な回復不足に陥る。このような状態では筋肥大効率は低下するし、何よりも健康的ではない。
体内の酸化ストレスが高いかどうかを判断する基準として血中グルタチオン濃度が用いられる。
活性酸素が身体に与える影響についてはこちらの記事で、抗酸化物質の作用とグルタチオンについてはこちらの記事で解説しているので参照してほしい。過去の記事では酸化ストレスは筋肥大に悪影響なので酸化ストレスを抗酸化物質で除去するという施策を提案した。
しかし活性酸素は筋肥大を引き起こす要因でもあり、場合によっては抗酸化物質の摂取が筋肥大効果を低下させる可能性も示唆される。これについて以下で解説する。
活性酸素が筋肥大に与える影響
トレーニングにより産出された活性酸素は、IGF-1を介したmTOR経路活性のトリガーとして筋肥大に貢献する。
SODをノックアウトさせたマウスを用いてC2C12細胞(筋芽細胞)での筋細胞の分化と肥大過程を観察した研究では、スーパーオキシドレベルが70%増加するとC2C12細胞が肥大したことが報告された。この研究からスーパーオキシドが筋肥大の内因性トリガーであることが分かる。
活性酸素はIGF-1シグナルの活性化とIL-6の分泌促進を通じて、骨格筋の筋肥大を誘導すると研究で示唆されている。
IGF-IがROSを誘導することが研究で確認されており、H₂O₂を用いた処理はIGF-I受容体(IGF-IR)のリン酸化を促進した。一方で抗酸化剤の投与がこのリン酸化を抑制し下流のAkt-mTOR-p70S6K経路をダウンレギュレーションさせることが報告された。
さらにIGF-Iにより通常は抑制されるFoxO1の活性(筋萎縮関連遺伝子Atrogin-1やMuRF1の発現)も、抗酸化処理によって再活性化されることが示された。
以上のことから、活性酸素はIGF-1を介したmTOR経路の筋肥大を活性化させるトリガーとして機能することが分かる。またこのトリガーは抗酸化物質を摂取することで抑制されることもわかる。
トレーニング後の活性酸物質摂取
トレーニング後に抗酸化物質(ビタミンCやビタミンE)を摂取することで、筋肥大が促進された研究もあれば抑制された研究も存在する。
このように結果に違いがあるのは被験者の属性やトレーニングに違いがあるからだ。なぜならトレーニングによる活性酸素筋肥大を活性化させるのは事実だが、それは産出された活性酸素が適切である場合に限るからだ。一定量の活性酸素であれば筋肥大に貢献するが、あまりにも多い量だと筋肥大よりも回復に身体が傾いてしまう。
トレーニングボリューム
抗酸化物質を摂取するかどうかの基準の一つとしてボリュームが挙げられる。
トレーニング中の酸素消費速度は安静時の10〜15倍に増加し、活動中の筋肉への酸素の供給量は100倍近くに達すると言われている。そしてROSの産出は負荷(強度×持続時間)に依存する。
例えば極端にボリュームが多い場合にはメリットを上回る量の活性酸素が産出されるため、トレーニング後若しくはトレーニング中の抗酸化物質の摂取が功を制す。
一方で高強度だが低ボリュームなトレーニングの場合は、高ボリュームと比較して活性酸素の産出量が少なくなるのでトレーニング後に抗酸化物質を取らなくてよい。なぜならこのようなトレーニングで産出された活性酸素の量は、活性酸素のメリットを享受する上で適切だからだ。ここで抗酸化物質を摂取すると活性酸素の量が下がってしまいIGF-1を介したmTOR活性を低下させてしまう。
1セッション当たりの適切なセット数は6〜10セット付近と分析できる。詳しくはこちらを参照してほしい。対象部位に対して2〜6セットくらいなら抗酸化物質の摂取は必要ないと筆者は考える。一方で10セット全てレストポーズを入れたり、2時間以上動くようなトレーニングの後なら抗酸化物質を摂取した方が良いかもしれない。
増減量
プログラムの目的が増量か減量かによって抗酸化物質の摂取基準が変わる。
例えばバルクアップを優先する期間にはトレーニング後に抗酸化物質を摂取しない。バルクアップ期間では筋肥大が目的であるし、炭水化物を減量期よりも多く摂取でき、コルチゾールを軽減することができるからだ。
減量期間の特に減量末期ならトレーニング後に抗酸化物質を摂取したほうが良い。なぜならこの期間の身体に筋肥大させる余裕は程ないからだ。この期間はアナボリックを求めるよりも回復に専念したほうが良い。
最後に
この記事では活性酸素の筋肥大メカニズムとトレーニング後の抗酸化物質摂取の是非について解説した。最後に内容をまとめる。
- 活性酸素は筋肥大の一因。
- 過剰な活性酸素は酸化ストレスと炎症を誘発。
- mTOR経路はROSにより活性化。
- ボリュームと負荷を基準とする。
- 増量と減量を基準とする。
この記事が読者の抗酸化物質摂取の判断基準として機能したならうれしい。
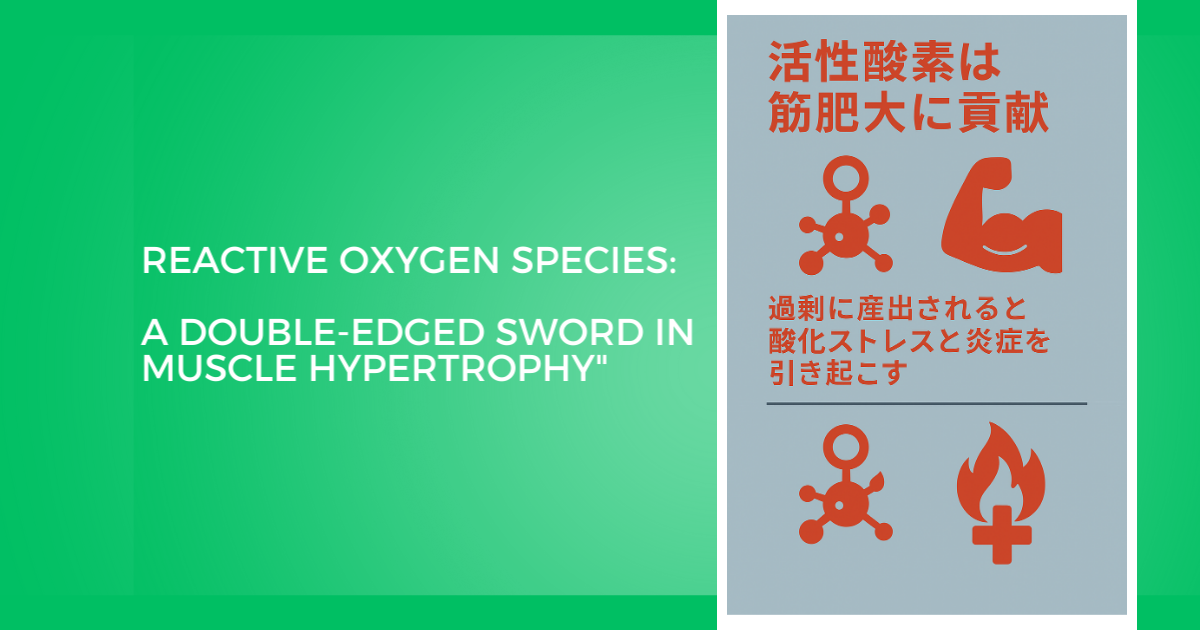
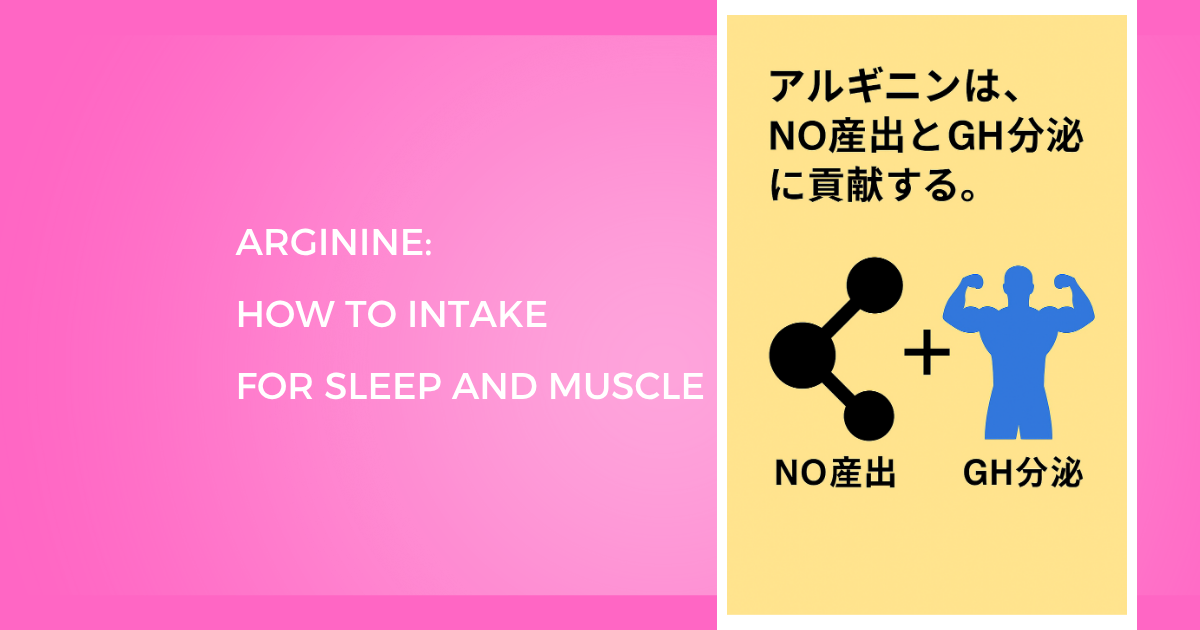
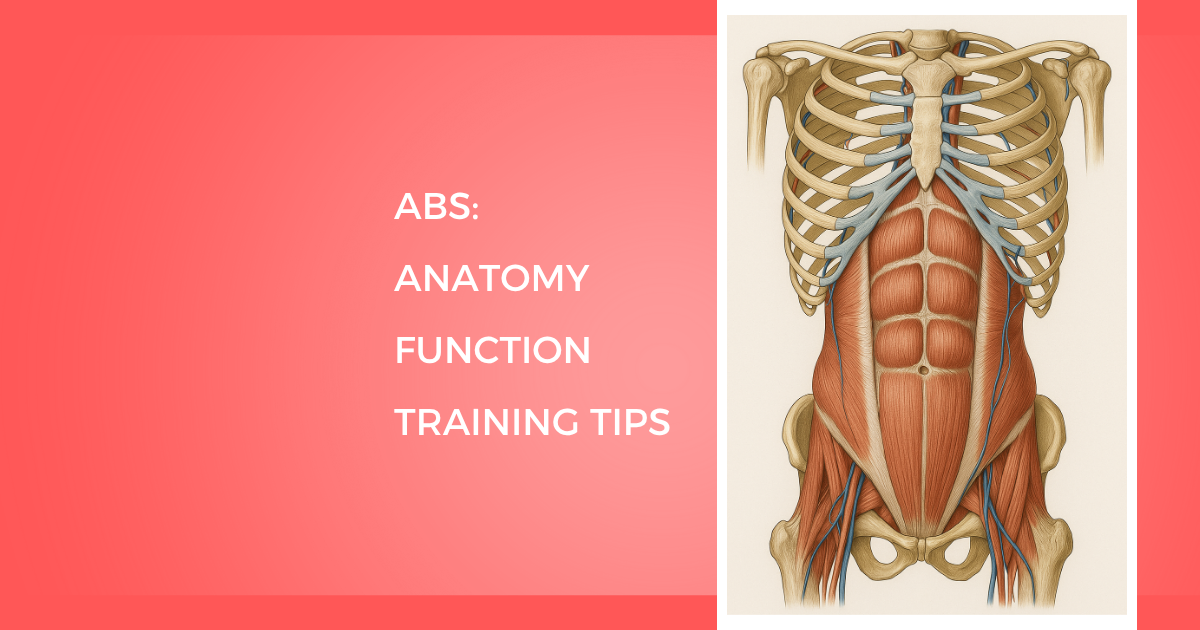
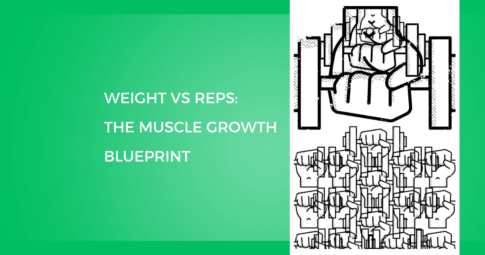
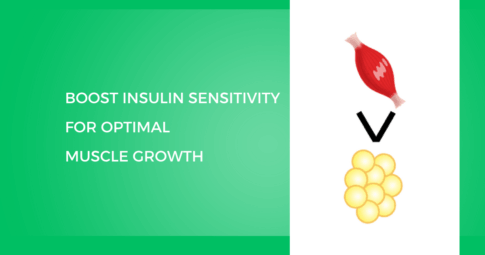

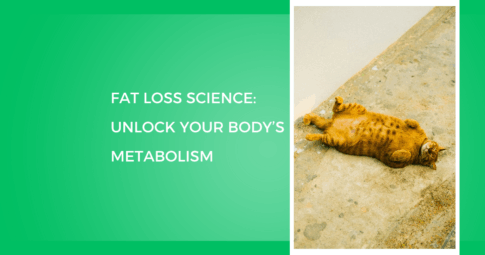
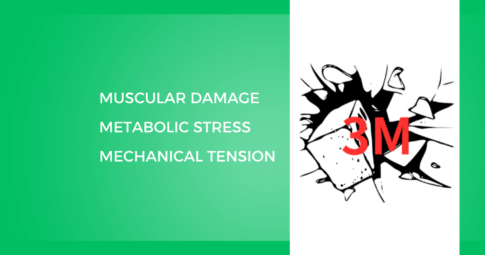
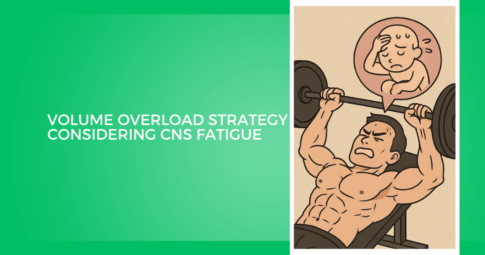
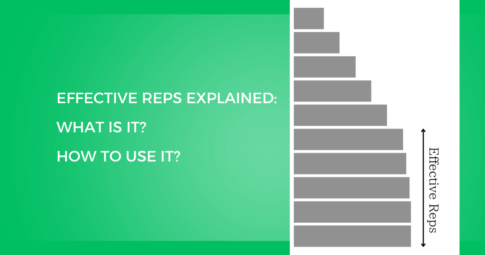





コメントを残す