このような悩みを持っていないだろうか。
・自分が初心者に当たるのか判断できない。
・何から始めるべきかが分からない。
・間違ったやり方でケガや失敗をしたくない。
この記事ではこのような悩みを解決していく。
この記事の内容は以下のとおりである。
1.初心者の定義と自己診断できる基準を解説。
2.初心者がするべきことを解説。
3.初心者が停滞しないために意識することを解説。
この記事を書いている筆者は筋トレを5年間行っており、ボディビルダーを目指し研究と実践を繰り返している筋トレオタクである。またフィットネスクラブでの勤務経験があり、初心者のシェイプアップに成功した経験もある。このような筆者が読者の悩みを解決しよう。
初心者の定義と自己診断できる基準を解説

このブログにおける筋トレの目的は筋肥大という点は前提として理解しておいてほしい。
ビッグ3
トレーニーのレベルを分ける基準としてビッグ3が用いられることがある。具体的にはスクワット100㎏で中級者、150㎏で上級者などである。
この基準の良いところはわかりやすい点にある。明確な数値でレベルが分かる。
ただこのブログではビッグ3をレベル分けの定義として用いない。なぜならデメリットがあるからだ。
一つ目は前提をいくらでも買えられる点にある。筋力と筋肥大(厳密には筋原線維肥大)には相関関係があるが、使用重量≠筋力である。前提を変えれば筋力に依存せずに使用重量を挙げられるので基準として用いることができない。
例えば骨格筋の力を最大限動員したベンチプレス100㎏と、サポーターやアーチ、手幅や可動域などを駆使した100㎏では、骨格筋への刺激がまるで違う。この二つを同じと扱う指標はこのブログにはそぐわない。
二つ目のデメリットは骨格の個体差を考慮していない点にある。具体的には150㎝のヒトの100㎏スクワットと180㎝のヒトの100㎏スクワットで膝関節にかかる負荷は後者の方が高い。絶対的数値を指標にすると骨格が小さい人の方が中級者になりやすくなる。しかし筋肉量は後者の方が大きかったりする。
トレーニング歴
これは少し考えると指標として用いられないことが分かる。例えばジムに10年通ってトレッドミルで歩いているだけのヒトと、真剣に3年間重りと向き合ったヒトがいて、トレーニング歴が長いから前者を中級者とすることはできない。
また「初心者ボーナス」という言葉を理由にトレーニングから3か月から半年も期間を初心者とする文献が日本語では多いが、あれは誤認である。実際は遺伝的限界の60%程度までは筋力及び筋肉量がのびやすいことを表しているだけで、そこに至るまでの期間はトレーニング強度や環境、仕事との関係などで変化する。
FFMI値
このブログではトレーニーのレベルをFFMI値で分ける。理由は骨格筋量を基準としているため今までの指標のデメリットを克服できている。
複数の文献から95%以上のヒトのFFMI値の限界は25±1%となる。そしてトレーニングをしていない一般的な男性のFFMI値は18%となる。さらに限界地の60%まではそれ以上よりも骨格筋の発達速度が速い。これらの特徴に基づくと以下の指標が完成する。
| レベル | FFMI範囲 | 対象者の目安 |
| 初級者 | 18.0〜22.0 | しっかりとシェイプアップできた身体。FFMI値22はコンテストに出ないなら十分。 |
| 中級者 | 22.0〜23.5 | コンテストを視野に入れる人が目指すレベル。生活におけるボディビルに捧げる時間は多くなる。 |
| 上級者 | 23.5〜25.0 | ボディビルとビジネスを結び付けたい、若しくは結び付けているヒトが目指すレベル。生活の7割はボディビルに捧げる。 |
このブログでは「FFMI値22以下」を初心者と定義する。
先の指標は男性を前提としており、女性にとってFFMI値とシェイプアップの相関関係は薄い。なぜなら女性は男性と比較して体脂肪が悪ではないからだ。例えばIFBBプロリーグのビキニカテゴリーでは過度な除脂肪はかえって評価が下がるといわれている。
女性の場合は体脂肪を利用してアウトラインを形成することもできるので、FFMI値でレベルを分けることはできないのだ。また女性はシェイプアップのために鍛えるべき部位とそうでない部位がある。そのため筆者はレベル分けなど気にしなくてよいと考えている。
初心者がするべきことを解説

トレーニング
まずは重量至上主義という考えを捨ててほしい。なぜなら筋肥大は使用重量の向上ではなくトレーニングボリュームを増加させることで達成されるからだ。
トレーニングと使用重量に関してはこちらの記事を読んでほしい。
次に漸進的過負荷について理解する。漸進的過負荷とはトレーニングボリュームを高めることであり、トレーニングボリュームは基本的に重量、回数、セット数、テンポ、インターバルで構成される。これらの要素のどれかを前回よりも何が何でも高めていくのだ。
トレーニングボリュームの構成要素に関してはこちら、重量回数に関してはこちら、セット数に関してはこちら、テンポに関してはこちらの記事を読んでほしい。
食餌とサプリメント
食餌とサプリメントに関してはマクロミクロを充足させることが第一優先事項である。サプリメントはこの前提がないと適切に効果を発揮しない。
食餌管理の基本中の基本に関してはこちらの記事呼んでほしい。
休養
初心者のうちは休養=睡眠と考えてもらってよい。睡眠はトレーニングや仕事などで継続的に高いパフォーマンスを発揮するうえ重要になる。
睡眠に関してはこちらの記事でまとめている。この記事で触れた内容の中からできることから始めていくと良い。最初から全部やろうとするのではなく段階的に身体を慣らしていくことが重要になる。
初心者が挫折しないために意識すること

ストレッチとウォームアップ
ストレッチとウォームアップを省略する人が多いが筆者は推奨しない。なぜならケガの可能性が高まるとともに筋肥大効果が結局低下するからだ。筆者は過去に左の大円筋を小断裂したことがあるが上半身のトレーニングが2か月まともにトレーニングできなかった。ウォームアップを5分10分やれば済む話である。
ストレッチとウォームアップに関してはこちらの記事を読んでほしい。ウォームアップに関しては特に上半身のトレーニングではローテーターカフのウォームアップは必ず行うこと。
継続できないベストより継続できるベター
筋肥大は数か月ではなく数年単位で行うことなので、短期間しかできない施策よりも長期間継続できる施策を講じる方が賢明である。特にほとんどの人が筋肥大を専業にしておらず、時間を捻出して筋トレ、食餌、休養を実施する。
以上のことからベストを追求するのではなくベターを目指す意識を持つと良い。100%を1か月実施するよりも80%を6か月継続したほうが結果は大きくなる。
最後に
この記事では初心者の定義から始まり、実際に何をすべきか、そして挫折せず継続するための考え方までを体系的に解説した。
初心者かどうかは骨格筋量に基づくFFMI値で判断する。トレーニングでは重量よりもトレーニングボリュームを重視し少しずつボリュームを増やしていくことが筋肥大には欠かせない。加えて食餌管理と睡眠といった基本の強度を高めることが不可欠だ。
筋トレは数か月で終わる短期勝負ではなく年単位で積み重ねていく長期戦なので、最初から完璧を目指すのではなく、ベターを見つけて取り組んでいく。
この記事が読者の悩みを解決できたなら嬉しい。
このブログはでは初心者(FFMI値22以下)のヒトが中級者(FFMI値22~23.5)にレベルアップするための知見を解説している。この記事内に盛り込んだ記事以外にも初心者に必ず役立つ知識と実践を提供しているので筆者のブログをぜひ読んでほしい。



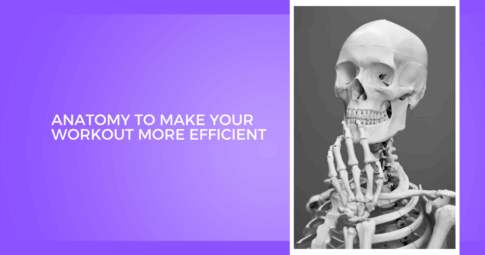
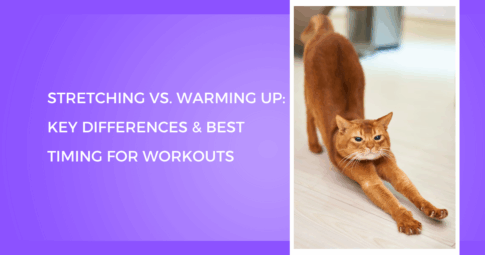
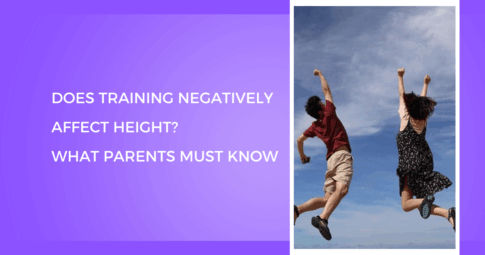
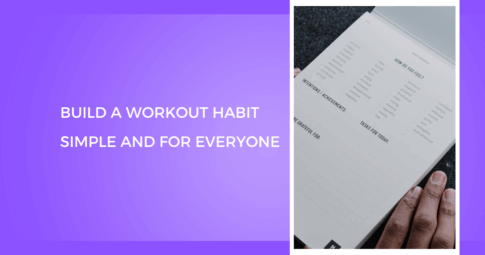








コメントを残す